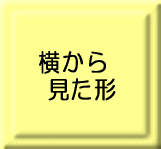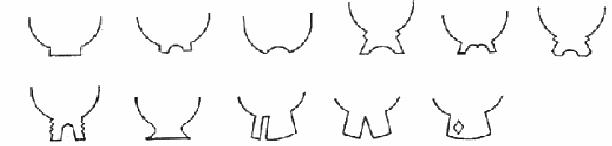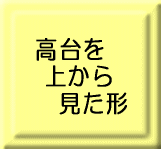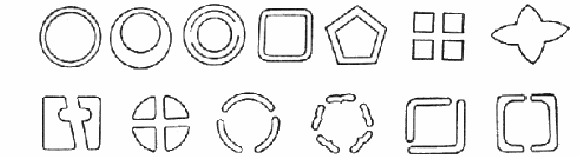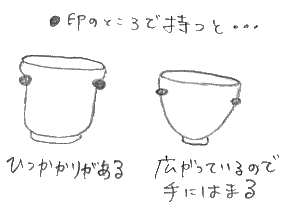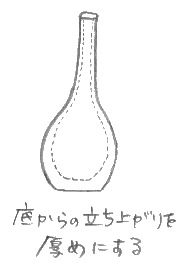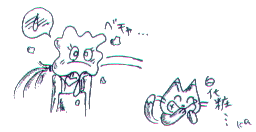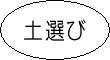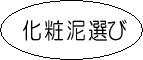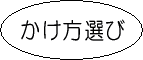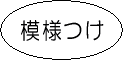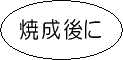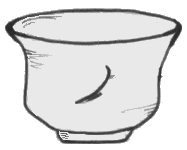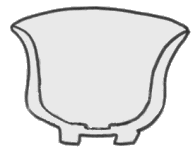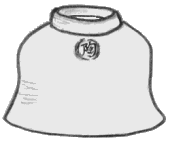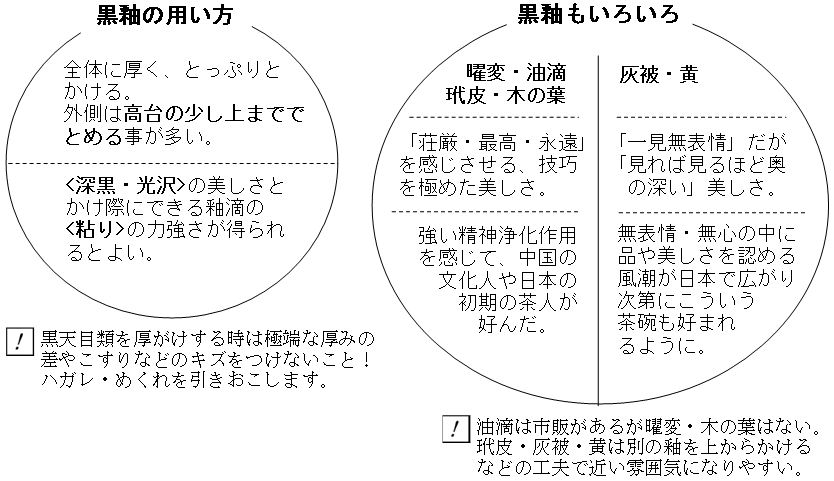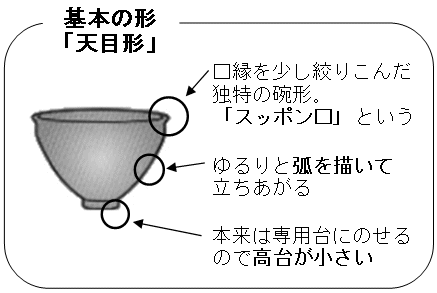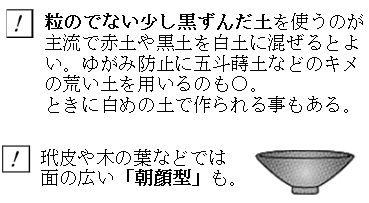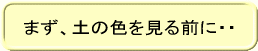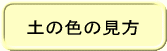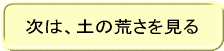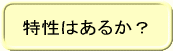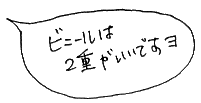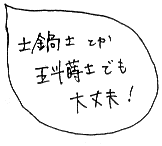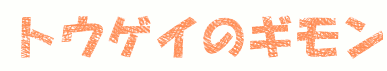 |
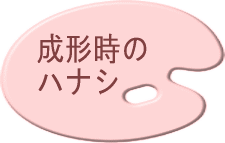 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
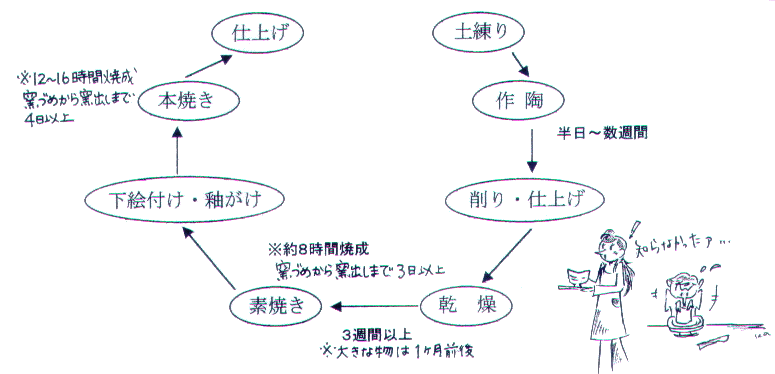
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
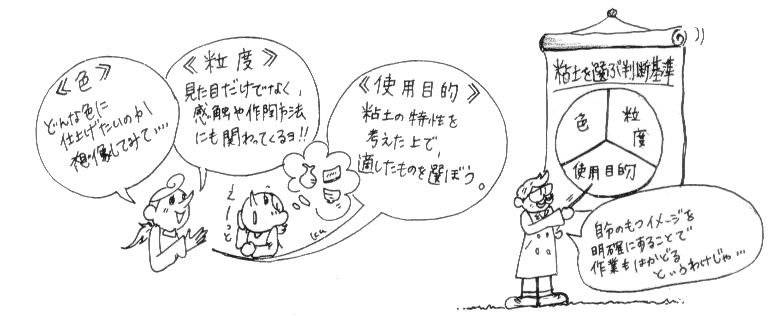 制作前の粘土選びは、とても大事です。 画用紙の色によって絵の具の発色が違うように、 粘土の色と質感も、釉薬の発色や全体の雰囲気を大きく左右します。 できれば、完成時にどんな色味に仕上がってほしいかをある程度イメージしてから、 それに合わせて粘土を選びましょう。 また初心者の方には、初めのうちは作りやすい粘土をおすすめします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
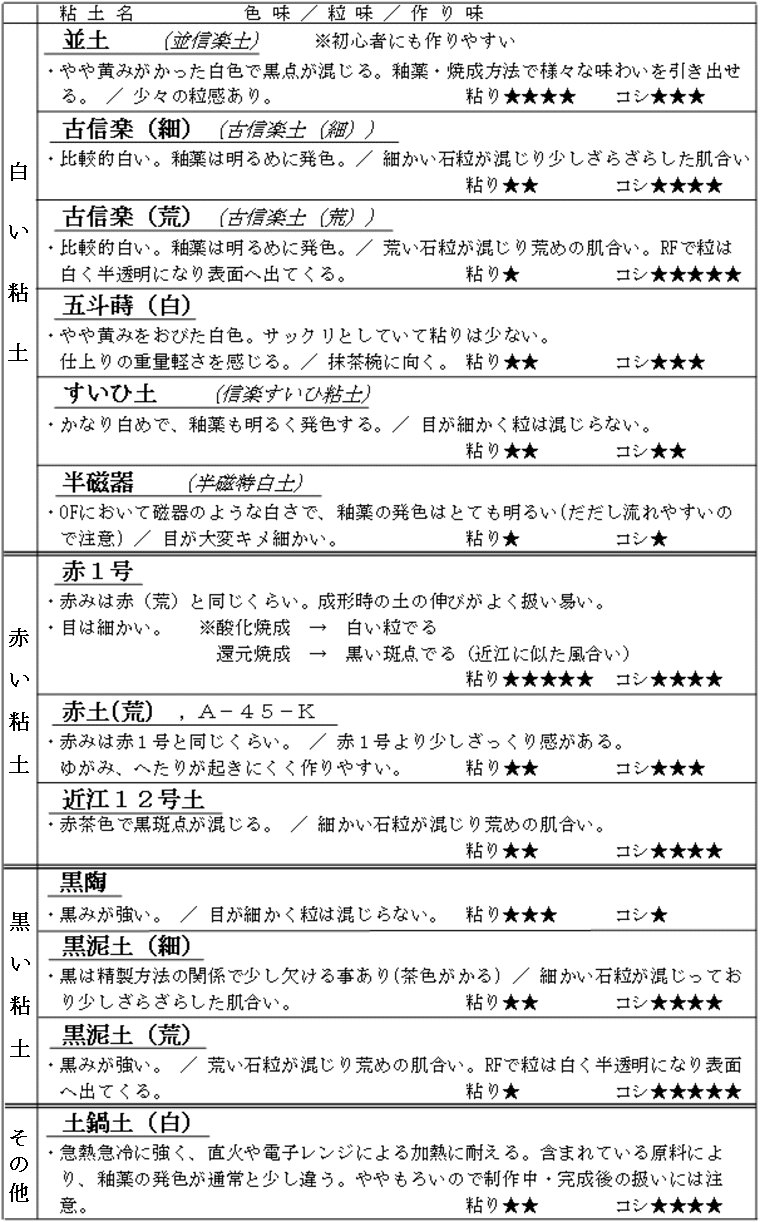 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窯に入るサイズの作品でなければ、焼成ができません。 当たり前の事だけど、作品をつくり始める前に必ず思い出して欲しい! と言うのは、 一生懸命つくったら、窯に入るより大きくなってしまった・・ という事件が、たまにあるのです、、 クラアート21で焼成できる、最大のタテ・ヨコ幅は下の通りです。 乾燥時にこの範囲内に収まる様に、制作をお願い致します。 もし、最大サイズぎりぎりや、特殊な形状のものを制作する場合には、 念のため、事前にスタッフへご相談ください。 (形によっては、範囲内のサイズでもうまく窯に入らない場合があります。) 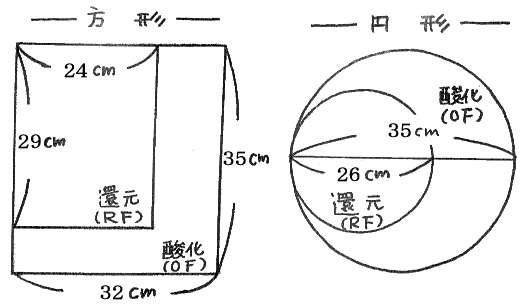 ※底面、胴回り、口縁のうちで一番大きい部分をこの範囲に収めてください。 ※酸化(OF)と還元(RF)では、使用窯が違います。 ※乾燥時のサイズは、成形直後から5%ほど収縮した寸法です。 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラアート21では、信楽土(白系・赤系・黒系各種)の他に、特性をもつ粘土が2種類あります。 そのうちの一つ、五斗蒔土(白)・・ゴトマキ土、は他の粘土に比べて焼きあがりが軽く、 保温性もあるので茶碗づくりに向いています。 軽さと保温性、その理由はざくざくとした土質です。 逆に、花器には向いていません。 みっちりと焼き締まる土ではないので長時間、水を入れておくことはできません。 粘りのなさ、砂っぽさがざっくりとした肌合いを自然に醸しだしてくれる、面白い粘土です。 下に、その特性や、作り味などを表記しています。どうぞチャレンジしてみてください! |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急熱・急冷OKの粘土です。 土鍋、グラタン皿、陶板ステーキ皿など・・ 直接火にかけたり、オーブン使用をしたい器は、この粘土でどうぞ! ※この粘土は、釉薬の発色がいつもと少し変わります。 教室内に、土鍋土だけの色見本がありますので、必ずご覧ください。 |
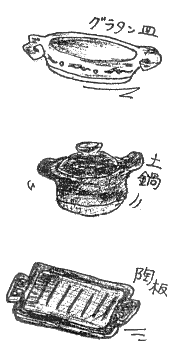 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作品をつくるにあたって、成形方法が色々とあります。 まずはそれらの利用ポイントをしっかりと知っておきましょう。 どんな形でもつくりやすいのは、ひもづくり。 平らな面の美しさを強調したかったら、板づくり。 同じ形を複数つくりたければ、ロクロ技法。 他には、外側の輪郭をしっかりとつくりこめる、くりぬき技法 内側からふくらむような力を感じさせる、玉づくりなど・・ それぞれに、できる事・良さがあり、 同時に、できない事もあります。 できれば一通り成形方法を学んでおくと 必要に応じてうまく使い分けたり、また、複数の成形方を組み合わせて、 自由な発想を形にしたり色々なことができるようになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
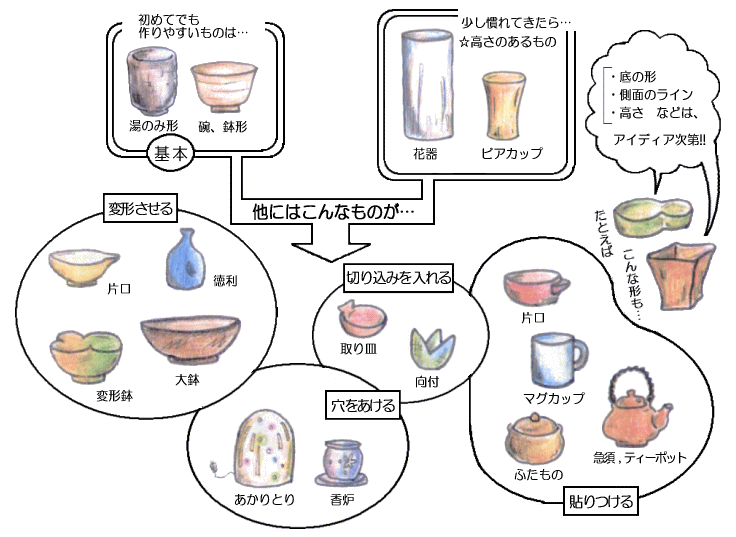 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
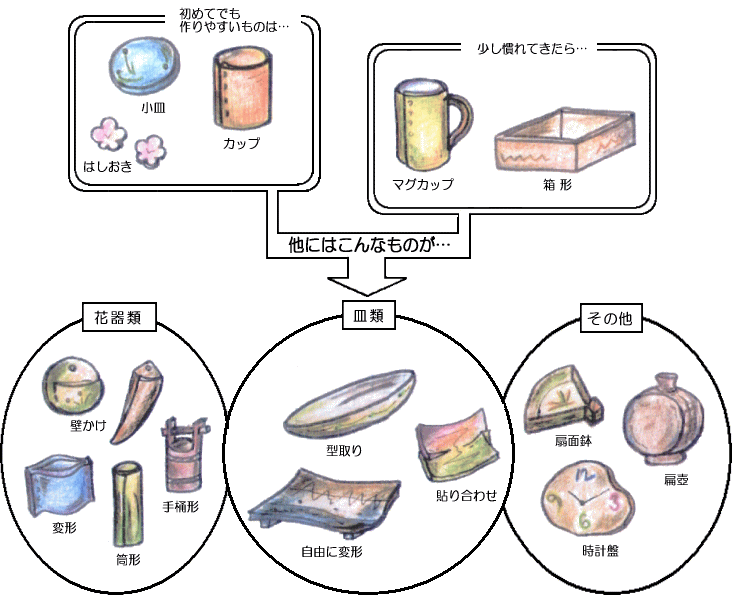 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
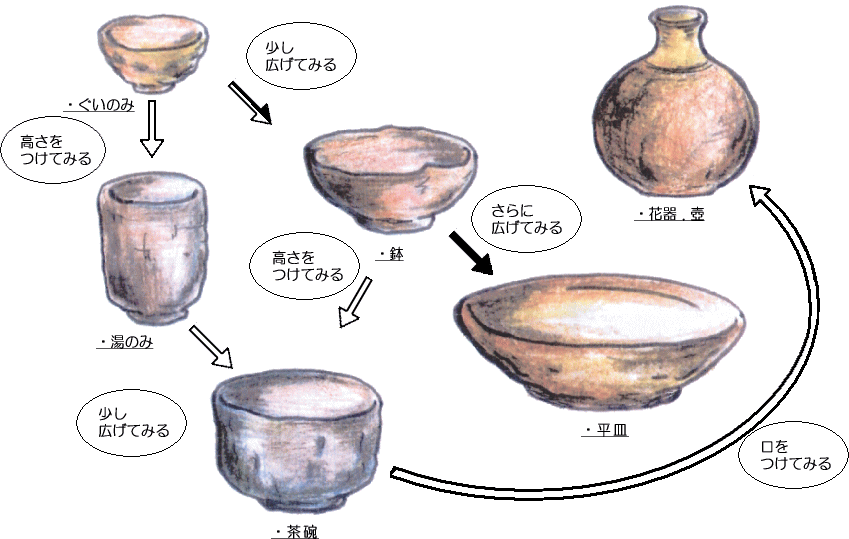 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
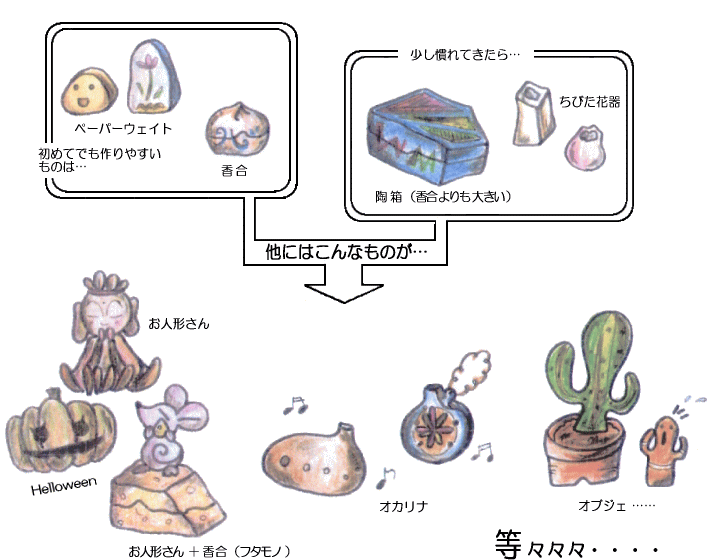 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底の形は、目立たないようで人間の足元と同じで意外と全体のイメージを左右します。 だから、高台にも工夫が要ります。 ただワッカ状に台をつける・・・のではなく、全体の形とのバランスをみながら 大きさは?高さは?傾斜は?・・・と、毎回ちょっと考えてみましょう。 高台が、本体の形に合わせた形になっていると全体の美しさもアップします。 また、昔の職人や茶人は、高台の形そのものにも工夫をこらしました。 色々なバリエーションを私達に残してくれています。それを真似してみる、のも面白いかも? 色々、遊んでみてください♪
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器をつくる時、軽く作った方がいいのは 手に取って使うもの…湯のみ・カップ・飯茶碗など。 逆に、花器、明かりとりなどは 持ち上げる必要はあまりないし、倒れにくくないといけないので むしろ重く作った方がいい。 軽ければいいというのではなく、用途・必要に応じて作り分ける事が大事です。 では、軽さ/重さの出し方のコツを少しご紹介します♪
軽さ・重さ両方のバランスが必要になります。 (倒れやすいと困るからです) そういうものには、口元を厚めにつくり、持ちやすくして底はしっかり作る… という風に、両方の要素を工夫して取り入れてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昔むかし、白いやきものが何よりも尊ばれた頃・・ 赤い土に、白い土をぬって白くみせようとしたことから「白化粧」の技法は生まれました。 今日では、ただ白くみせるためだけでなく その上に絵を描いたり、かけ方を工夫したりと色々な使い方がされています。 普通は赤土や黒土にかけて色の対比を生かしますが、時にはわざと白い土にかけることもあります。 小さな工夫・使い方で作品はパッと個性的になります。 制作の流れにそって、できることを下に示しましたので気軽にトライしてみてください!
本当に色々なことができる、白化粧です。 最後に、かける時の注意事項があります。 かける時、かける作品の乾燥状態、化粧泥の濃度、作業の速さが大事です! 初めての方は、必ず先生に要領を教わってください。 適切な状態で作業しないと、白化粧ははがれたり、、あとで釉薬がちぢれたり、一番怖いのは、作品が水分を吸ってこわれてしまったり! 何度かやってみて、その要領を覚えてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抹茶碗をつくってみましょう! 難しそう…と、すぐに思わないでください。 基本的には湯のみやカップと変わりません。 本当です。飲みやすくて、持ちやすい器であること・・それが一番大事なのです。 そして、それに加えて、お茶を点てやすいような形にしてあげる。それから、更に余裕があれば、どの側でもいいから見どころを一方向につける。 これで、立派な抹茶碗の出来上がりです〜! そんなに制約がないことが、お分かり頂けたでしょうか? ぜひ、自分なりの色や形で、抹茶碗をつくって楽しんで頂きたいです。☆ それでは、飲みやすさ・持ちやすさのためのポイント、 それから、お茶を点てやすくするポイント、魅せるためのポイント。 ご紹介します。
抹茶碗は、おもてなしの心の世界で その瞬間にいるすべての人の想いをつないでくれる、道具なのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昔から引き継がれている、抹茶碗の形もあります。 茶人に好まれたもので特に代表的なのが、 きりりと端正な、唐の茶碗。 ぽってりと素朴な、楽茶碗。 豪快な遊び心を感じさせる、桃山茶碗。 柔らかく堂々と広がる、高麗茶碗。 どこの陶業地にもオリジナルといえる形や色があるのですが、 それはその土地の粘土・釉薬の長所を最大限に生かそうとする努力と そこに生きる人々の美意識とが合わさってたどり着いた、一つの形式のようなものです。 それらの型は、その土地のやきものの個性として、またシンボルとして今も大切にされており、 そしてその中でも、昔の目利きの茶人が好んだものは、時代を越えて愛され続けています。 今、どんな土・釉薬でも手に入り、 色々な文化・スタイルがあふれる中で生活している私達ですが 昔の抹茶碗の、土地で採れる原料のみを使って、その時代・その土地独自の感覚を表現しきったその強さ・美しさにもまた、魅了されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お茶を飲む習慣は中国から伝わりました。技巧の高い中国製茶碗の美しさや「心を清め浄化させる」という精神修養的な要素に日本の文化人も魅了されて、唐物を用いた「茶飲み」はやがて日本独自の「茶の湯」の文化へと発展していきます。 唐物茶碗、といえば何といっても黒釉です。青磁や白磁よりもお茶の色をひきたてて心にも響く…ということに中国の人々は早くから気付いており、その美意識は日本へも引きつがれました。 当教室にある黒天目・油滴天目はこの「黒釉」の類です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「楽焼」という言葉は現在広い範囲で使われていますが、本来は京都の樂家で焼かれたものをさします。 素焼きよりちょっと高いくらいの温度で焼き上げるので、独特の柔らかさを感じさせるやきものです。 1250℃の高温焼成では土がカチッと焼きしまってしまうので、楽焼の柔らかい質感は得られませんが、 長く愛されてきた楽茶碗の形状や独特の感覚は抹茶碗としての参考に留まらない魅力をもっています。 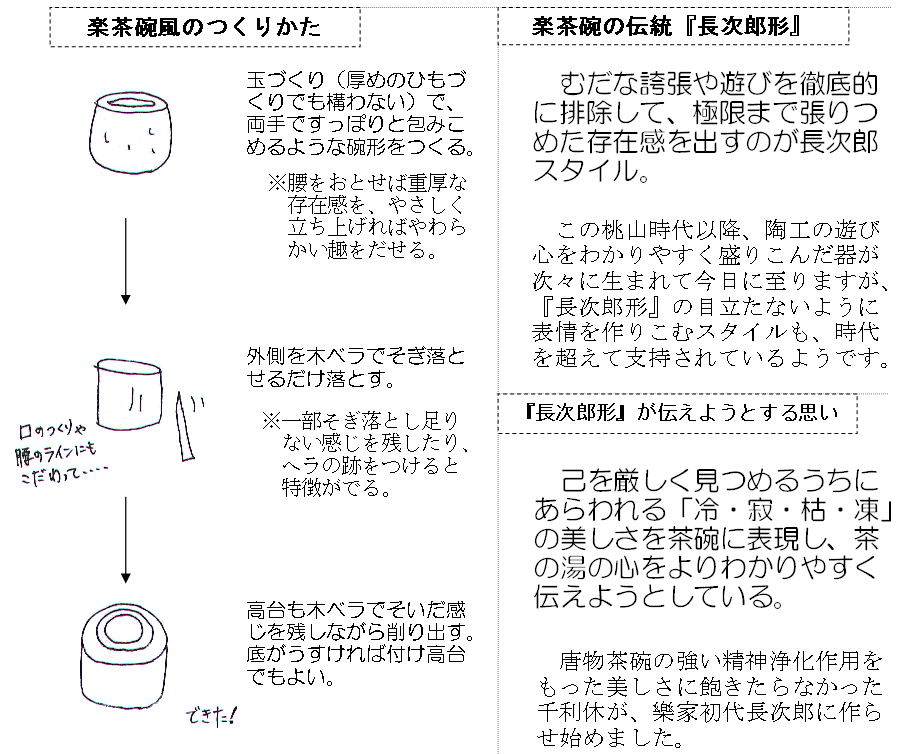 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃山時代に美濃(岐阜)でつくられた茶碗は創意に満ちて遊び心いっぱいです。 瀬戸黒・志野・織部・黄瀬戸といった特徴ある釉薬、軽妙な絵筆のタッチ、全方位にわたって観る者を楽しませるフォルム。 ほぼ同時期に生まれた楽茶碗と対称的なそのわかりやすさ、親しみやすさは美濃茶碗が権力者たちを中心とした茶の湯の世界からではなく、町家の一般の茶人の”手に入りやすい茶碗がほしい”というニーズに応えて生まれたからこそ…のようです。 数百年たった現代でもその斬新さは失せないまま日本の独自の美意識を伝えています。志野釉や織部釉を用いる時、それらの特徴を知っておくと役立つかもしれません。 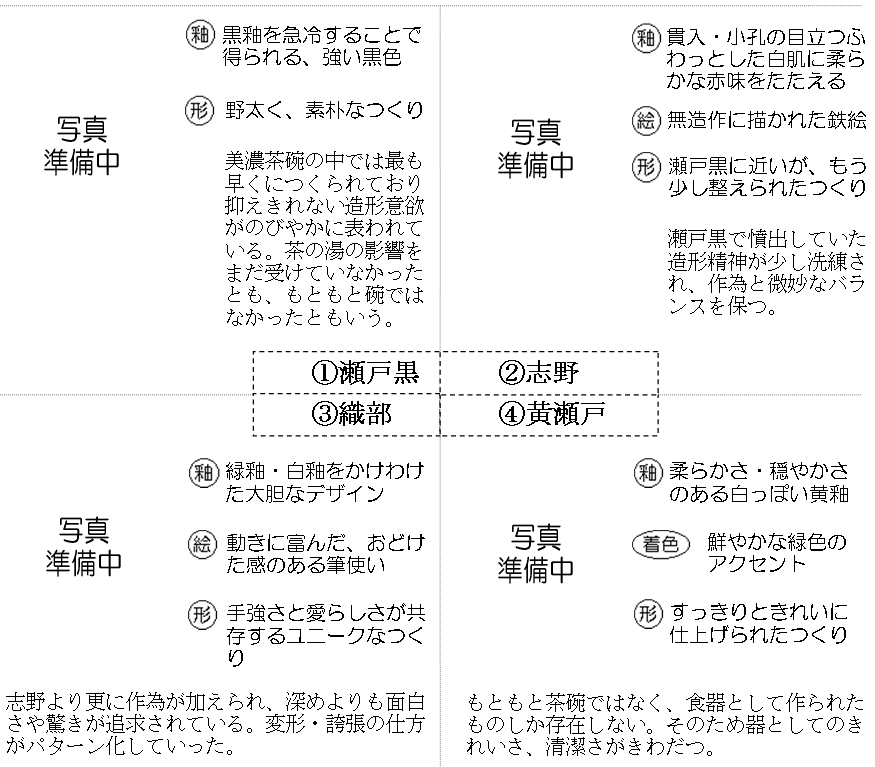 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高麗茶碗とは朝鮮でやかれた茶碗のことで、もともとは日用雑器として日本に入ってきたものでしたが、その姿や釉景の良さを見出した茶人が抹茶碗として使うようになり、唐物(中国製)に次いで尊ばれるようになりました。種類は井戸形のもの・白化粧を用いたもの・日本の好みをうけた注文品…など色々ありますが、どれにも共通するのはその大らかさ・素朴さ・それでいて崇高なまでの風格で、茶の湯に親しむようになっていた武将たちの気風に、そして流行りつつあった侘び茶の好みにもとても合っていました。中でも抜群の人気を誇っていたのは『井戸茶碗』で、その形を模したものが唐津や萩を始め日本の各地で多種多様に作られたほどです。 ここではその井戸茶碗の特に形状について紹介し、これまで取りあげてきた唐物茶碗・和物茶碗(楽/美濃系)と同様に茶碗を楽しんで作る際のヒントにしていただければと思います。 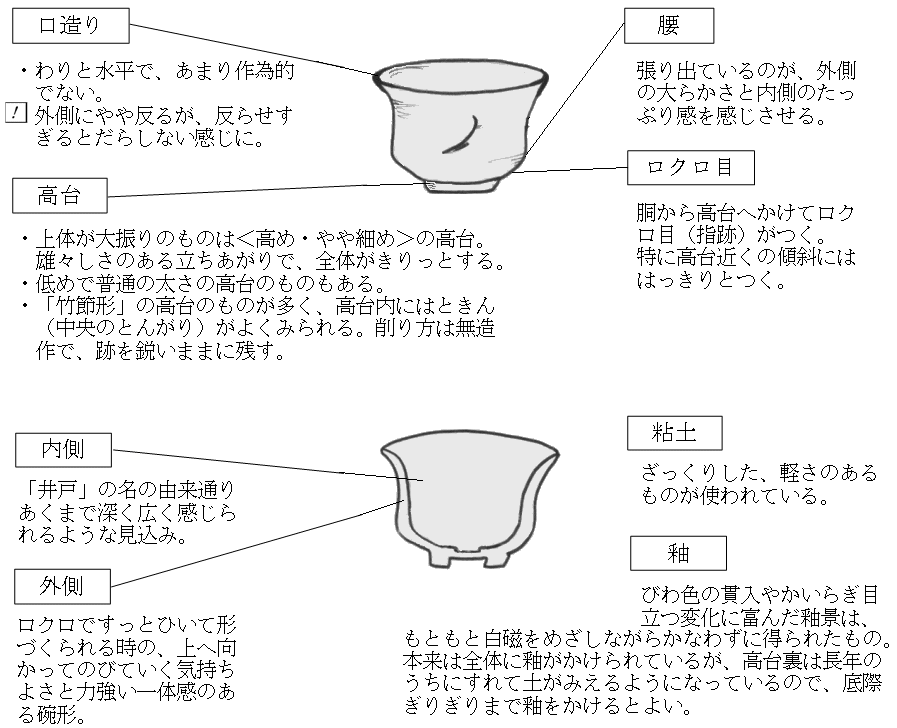 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌や店頭などで気に入った器を見つけると 同じようなものを、すぐにでも作りたくなりますね〜(^^) その時にまず大事なのは、それがどんな粘土で作られているか、を見ることです。 器を裏返せば、大抵は無釉になっていて粘土のそのままの色を確認できます。 もちろん、その作品に使われている土と正確に知ろうとしたら難しいかも・・ 陶芸大国日本、粘土の種類は沢山あります。 でも、目的は似た感じのものを作ることなので、「その土と大体同じような色・質感を得るには教室のどの粘土を使えばいいだろうか?」 そんな視点で、器の底裏を見てみればいいのです。
こんな風に使われている粘土の種類を見ていきます。 そしてその後は、 技法・・ (白化粧/象嵌/線描/etc.) 絵の具・・ 釉薬の色・・(透明/織部/乳白/etc.) と、作る順番でその工程を想像しながら、作り方を今度は全体を見ていってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘土は固くなると使いづらいですね。 前に買った『残り粘土』が、まだやわらかければ気持ちよ〜く 作陶できるのだけど… 時々、妙に固くなってたりして。 だからといって処分してしまったら、もったいないです。 長い年月かけて地中でつくられ、ようやく自分の手元に届いた粘土… 大事に使ってあげてください。 新しい習慣一つで、粘土をいつまでもやわらかく保つ事ができます。 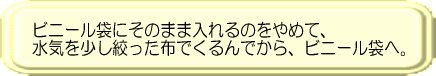 これだけです! タオルだと、時間が経って布が傷んできた時に繊維が粘土にくっついて苦労することもあるので、 さらしとかシーツの布がお奨めです。 ただし保水力がタオルよりも落ちるので、薄手の布を用いる時は水気を少し多めに含ませてあげてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントは「待つ」それだけ…。 固いうちに無理無理練ろうとすると大変です。この方法がおすすめです。 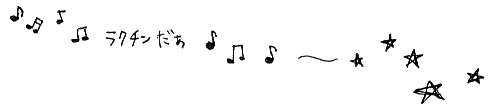
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウゲイのギモン目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||